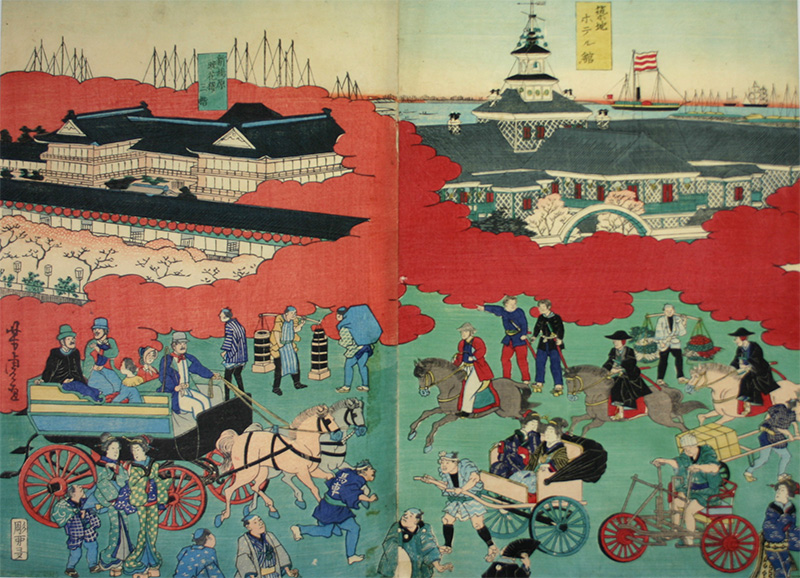2025.05.08
公共交通インフラはもう必要ないのか ――遅れている「持続可能な移動」、イタリアに学ぶ「国が前に出ること」
The Public-transport Infrastructure for Sustainable Mobility ――A Turning Point, When the Nation Should Step Forward: Learning from Italy as “Slow indicator”
1 / 7ページ
【 PDFで閲覧する場合はこちらから 】
■4分の1世紀、時代の節目
しばしば、100年単位の世紀は4分の1世紀くらい経過すると、その時代の潮流とも呼べるような大きな流れが見えてくるといわれる。19世紀は蒸気機関の発明により産業革命が進展した時代だが、1825年にはその先駆け的な動きとして蒸気機関車による世界最初の鉄道が英国ストックトン~ダーリントン間で開通した。20世紀では第1次世界大戦の終結(1918年)後、民主主義が広がる一方で大衆の支持の下での全体主義も新たな政治体制の1つとして生まれつつあった。1922年にイタリアでムッソリーニによるファシスト政権が誕生、ヒトラーが政治信条を明らかにした著書『我が闘争』上巻を刊行したのは1925年だった。
そうした歴史の流れや、世界で現在起こっている事象などを想起すると、2025年は後世の歴史家から、大きな分水嶺の年だったと指摘されるかもしれない。ウクライナ戦争は膠着したまま2月で3年目に入ったが、米国では地球温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定から離脱し、多くの国が推進してきた気候変動対策を反故にするなど、近年の政権とはかなり異質の自国中心の政策を掲げるトランプ政権が誕生。国際平和や民主主義のあり方が問われているからだ。もちろん、わが国を含め世界が良い方向に向かうことを祈らざるを得ないのだが……。
そんなことを改めて感じさせてくれるのは今年が21世紀で4分の1世紀が経過した年であるとともに、昭和の元号で100年に当たり、太平洋戦争終結からも80年目という節目の年でもあるからである。石破茂首相も1月24日の衆参両院本会議で行った施政方針演説で「今年は戦後80年、そして昭和の元号で100年に当たる節目の年。これまでの日本の歩みを振り返り、これからの新しい日本を考える年にしたい」と述べた。
この演説の中で賛否を含めて話題を集めたのが、今後の日本について「楽しい日本」を目指すべきとしたことである(この「楽しい日本」というキャッチフレーズは故・堺屋太一氏の著書(『三度目の日本 幕末、敗戦、平成を越えて』からの引用である)。
■令和の列島改造、肩透かしの「インフラ整備」
「楽しい日本」は明治維新期の「強い日本」、戦後の高度成長期の「豊かな日本」に次いで日本が目指すべき目標と位置付け、「すべての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦し、『今日より明日はよくなる』と実感できる……活力ある国家だ」としている。その「楽しい日本」を実現するための「政策の核心」としているのが「地方創生2.0」である。
「地方創生2.0」とは何か。道路や鉄道などハードのインフラ整備を中心にした田中角栄元首相の「日本列島改造」に対し、「令和の日本列島改造」と名付け、ハードだけではなくソフト的な取り組みにも力を入れることで新たな人の流れを生み出し、東京への一極集中を是正していくという。「令和の日本列島改造」は具体的には5つの柱からなる。①若者や女性にも選ばれる地方②産官学の地方移転と創生③地方イノベーション創生構想④新時代のインフラ整備⑤広域リージョン連携――である。列島改造を掲げるだけあって、デジタル技術にこだわったきらいがある前政権の「デジタル田園都市国家構想」と比べると、トータルな視点での国土政策を目指していることをうかがわせる。とりわけ、「広域リージョン連携」は「都道府県域を超えた広域連携の新たな枠組み」としており、これまでの地方創生の施策ではあまり焦点が当てられていなかったものである。
ただ、それらを具体化する取り組みとなると、2地域居住のための「ふるさと住民登録制度」検討や、「官が一歩前に出る」とした防災庁など政府関係機関の地方移転など注目される施策もあるが、多くはこれまでの延長線上か、抽象的なレベルにとどまっている。
田中角栄元首相の列島改造と比較する意味でも「新時代のインフラ整備」は期待したいところだが、施政方針演説では「GX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)を支える『新時代のインフラ』を軸として、産業拠点や生活拠点の再配置を促進する」と従来の施策の域を出ていない。ローカル鉄道の縮小など地域交通をめぐる深刻な問題には抜本的な制度改革どころか、何ら言及されなかったのは肩透かしを食わされた感がある。
交通分野なのに「新時代のインフラ整備」ではなく、「若者や女性にも選ばれる地方」の中で述べられたのが自動運転である。「暮らしやすいまちづくりには、官民でAI・デジタル技術を活用し、地方の持続可能な生活インフラを作っていくことが重要」と前置きしたうえで、「自動運転の実装加速に向けた制度整備を進める」と短いながらも言及した。
肝いりの地方創生に文字数で施政方針演説の3割を充てたというのは独自性の発揮として評価したいが、その地方創生の要であるはずの交通や移動についての言及が自動運転だけというのは何とも寂しい。
自動運転はその是非を含め、今後の交通社会のあり方を大きく左右する重要なテーマである。地域の公共交通の制度改革もそうだが、推進の旗を掲げるとしても、国(または政治)こそがこの問題について大局的な視野に立って広く国民に訴える議論を巻き起こすなど、「前に出る」覚悟が必要ではないだろうか。