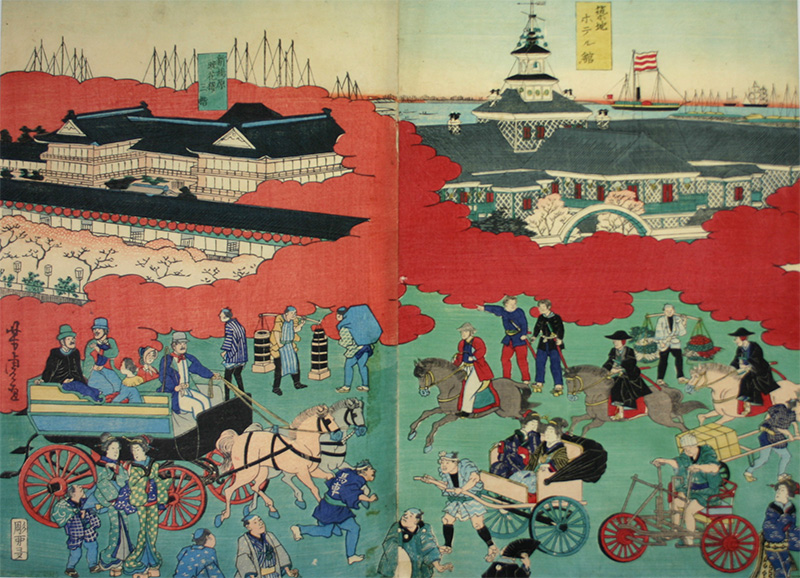2025.05.08
公共交通インフラはもう必要ないのか ――遅れている「持続可能な移動」、イタリアに学ぶ「国が前に出ること」
The Public-transport Infrastructure for Sustainable Mobility ――A Turning Point, When the Nation Should Step Forward: Learning from Italy as “Slow indicator”
2 / 7ページ
■持続可能な移動のためのインフラ整備は国主導で、遅れたイタリアでも動き
こうした「国がもっと前に出るべき」とする考えは、欧米なかでも欧州の動きを見ると、その感をますます強くする。コロナウィルス禍以降もクルマ社会の弊害に立ち向かうための公共交通インフラ、なかでも鉄軌道の充実強化に向けた行政側の取り組みが続いている。というよりは、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)の中、国によってはその動きはかえって強まっているともいえる。その動きは欧州の行政当局において普及している言葉を使えば、「持続可能な移動の実現に向けたインフラ整備」なのである。そして、それを主導しているのはEU(欧州連合)であり、国なのである。
日本ではメディアを含め、主に財政効率を理由に「新たにインフラを整備する時代は終わった」とする論調が支配的であるが、何でもかんでもインフラ整備を目の敵にする考え方はいかがなものだろうか。欧州が目指し、取り組んでいるのは先ほども述べたように「持続可能な移動実現に向けた公共交通インフラ整備」なのである。その代表がトラム(路面電車)など魅力的な地域公共交通システムの整備である。
その整備支援で先行するドイツやフランスの取り組み1)は日本でも知られているが、近年、注目したいのは欧州主要国の中でも鉄軌道への投資が遅れていたイタリアである。
「地域公共交通再生の切り札」ともいわれるトラムの導入において、イタリアは同じラテン諸国でも先頭を走るフランスに比べ大きく遅れをとっていた。それが近年、「トラム・ルネサンス(路面電車の復活)」と呼ばれるような流れに転じている。新たにトラムが復活したり、トラムの路線網を広げたりする都市が増えているのだ。
トラムは第2次大戦後、世界的な自動車の普及に伴い、「道路交通の邪魔もの」として各国で撤去が相次いだが、イタリアも例外ではなかった。かつては約80都市でトラムが走っていたが、1960年代には14都市まで減ってしまったといわれる。
しかし、そうした縮小の流れが変わってきた。1990年代以降、欧米ではクルマに依存しすぎないためのまちの活性化策としてトラム導入の動きが急速に広がってきたが、イタリアでもその波と無縁ではなくなってきた。21世紀に入り、車両の超低床化をはじめハード・ソフトともに「次世代型」である新たなトラムの開業が相次いでいる。
EUの経済支援を受けて、シチリア島東端の都市メッシーナ(開業は2003年4月)を皮切りに、サルデーニャ島のサッサリ(2006年10月)、カリアリ(2008年3月)の2都市でも開業。2007年3月には北イタリアの古都パドヴァではゴムタイヤ式のトラム(正確にはトラムではなく、トロリーバスに近い)が導入された。同じ北イタリアの都市ベルガモでも2009年4月から、かつて鉄道が走っていた線路を活用したトラムが郊外路線として運行されている。
そして、2010年2月にはイタリア・ルネサンスを代表する古都であり、現在はトスカーナ州の州都であるフィレンツェでも約50年ぶりに隣町とを結ぶ郊外路線としてトラムが復活した。同じ2010年12月にはヴェネツィアと言っても本土側のメストレだが、パドヴァと同じゴムタイヤ式トラムが誕生。2015年9月にはメストレ中心部から、ラグーナ(潟)に架かる長大なリベルタ橋を渡ってヴェネツィア本島のローマ広場までの新たな系統が開業した。さらに、先ほどのフィレンツェでは当初の予定よりもかなり遅れたが、なかと大学病院、空港を結ぶ新たな路線も2018年から2019年にかけて相次いで誕生した。
トラム開業の動きはシチリアでも広がっている。長い間、工事が続いていた州都パレルモでも4路線、計17㎞に及ぶ路面電車の運行が2015年に始まった。イタリア全土における現在の開業都市の数は、ミラノなど古くから存続する6都市に、新規開業した8都市を加えた計14都市(総路線距離は約210km)に上り、1960年代の水準まで戻ってきた。
■持続可能な移動に向けた国家戦略プランを策定
そうした中で見逃せないのは、イタリアの中央政府が近年、持続可能な都市交通プロジェクトへの支援に大きく舵を切ったことである。その大きな契機になったのが、2018年12月に公表した「持続可能な移動に向けた国家戦略プラン」(Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile) だった2)。これに基づき、2019年国家予算で2033年までの15年間という長期にわたる予算措置を保障する法律が制定された。
元々は2019年半ばまでに財源保障を申請した自治体が対象だったが、その後、2021年1月まで申請期間が延長された。それを後押ししたのが、コロナ対策の1つとしてEUが打ち出した総額7,500億ユーロの復興基金「次世代のEU」だった3)。イタリア政府の支援額にこのEUの「コロナ復興基金」が上積みされたことで、予算措置が充実したのである。
EUの「コロナ復興基金」なども加えたこうした充実した財源を元手に、ボローニャやブレーシャ、レッジョ・エミリア、ピサ、トレント、ボルツァーノなど北イタリアを中心とする10近くの都市がトラムの復活(新規導入)・路線網拡大など地域公共交通の強化に取り組み始めている。こうした国側の強力な財政支援により、イタリア国内で新たに186㎞のトラム路線が整備されるという。大半は財政が比較的豊かな北・中部地域に集中している。このうち、ミラノに次ぐロンバルディア州第2の拠点都市であるブレーシャ(人口約20万人)は既に無人自動運転の地下鉄を2013年に開業したが、新たに2つのトラム路線を市内に建設することで注目されている。

1) 両国とも地域公共交通整備・運営のための基本的な法律や、それに基づく独自財源制度が今から50年以上前からある。ドイツでは1971年に制定された「都市交通改善助成法」(現在は別の法律)により、国税の鉱油税(ガソリン税)のかなりの部分が近郊鉄道や地下鉄、トラムなど近距離旅客交通の整備・運営のための安定的な財源として州政府を通じて割り振られている。一方、フランスでも同じく1971年から複数の基礎的自治体(コミューン)からなる広域都市圏政府が課税主体となる法定任意税としての交通税(交通負担金)が導入され、トラムなどの整備だけでなく運営の主要財源になっているが、これら財源制度を支える基幹的な法制度として、1982年に施行した「国内交通基本法」(LOTI)がある。この中で自治体による保障義務として国民の「移動権」が明記されている。詳細は市川嘉一『交通崩壊』(新潮新書、2023年刊)を参照。
2) 地域公共交通サービスや大気の質改善を目的にした長期間の予算保証を伴った革新的な計画として、国内自治体からも評価されている。
3) EUの復興基金を活用するため、イタリア政府がドラギ政権時の2021年にEUの行政機関である欧州委員会に提出したのが、「PNRR」と呼ばれる復興パッケージ「再興・回復のための国家計画」(Piano Nationale di Ripresa e Resilienza)である。提出した計画は計2,351億2,000万ユーロの投資計画となっており、補足部分としてのイタリア政府の独自財源を含めた3種類の財源で構成されている。計画内容では①デジタル化、イノベーション、競争、文化及び観光②グリーン革命及び環境移行③持続可能なモビリティ(移動)のためのインフラ④教育と研究⑤包摂と結束⑥健康――の計6つの柱からなる。持続可能なモビリティのためのインフラの予算額は3番目に多い314億6,000万ユーロ(全体の13.4%)で、このうち補足ファンドとしてイタリア政府は60億6,000万ユーロを予算化した(ジェトロ「ビジネス短信」から引用)。