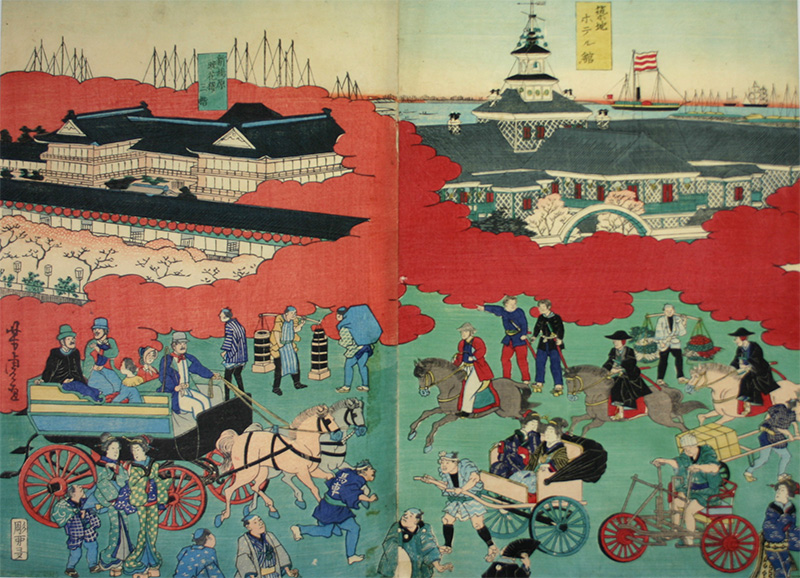2025.05.08
公共交通インフラはもう必要ないのか ――遅れている「持続可能な移動」、イタリアに学ぶ「国が前に出ること」
The Public-transport Infrastructure for Sustainable Mobility ――A Turning Point, When the Nation Should Step Forward: Learning from Italy as “Slow indicator”
6 / 7ページ
■「4分間隔」の高頻度運行など高い利便性と、支え役としての公的資金
トラムの利便性は高く、例えば、最初に開業したT1路線の場合、運行間隔は平日の日中時間が4分に1本、日曜や休日でも9分に1本とかなりの高頻度運行である。筆者もこれまで何度も平日の日中にも乗車したが、運行時刻はほぼ正確で、しかも頻繁に運行されていることを実感している。
人口密度の高い大都市ならいざ知らず、フィレンツェのような中規模都市でもクルマに慣れた市民らを公共交通の利用に向かわせるには、4分に1回という高頻度運行が必要になるということなのだろう。平日の始発時間は朝5時で、最終は0時半であり、運行時間は欧州の主なトラム運行都市と同様、ほぼ1昼夜にわたる。
運行会社のGESTは毎年、利用客を対象にした満足度調査(対面調査)を実施しているが、調査結果からも高頻度運行などトラムの利便性の高さがうかがえる。2024年9月実施の調査(有効回答は約1,800人)ではトラムの運行サービスに対する10段階評価で平均点は8.3点、満足度は98.9%と高い数字を上げている。スリなど安全面や苦情への応答、車内混雑に関する評価は6点前後だったが、それ以外の項目では評価が7点以上と高く、最も高かったのは定時性の8.8点と高頻度運行の8.7点だった。
こうした利便性の高いサービスの実現により、通勤などでマイカーから乗り換える市民も増えている。GESTの2019年調査によると、トラムの利用以前に使っていた移動手段を尋ねたところ、有効回答の中で最も多かったのはバスの40%だったが、マイカーは19%とそれに次いで多かった。
利便性の高い公共交通サービスを市民らが享受できるのも、目先の採算に悩まされることがない公的サービスとして提供し、そのための充実した運行財源があるからこそである。運行費は2024年度実績(T1路線とT2路線の2路線)で5,010万ユーロ(約80億円)だが、このうち運賃収入は39.3%と4割弱で、州の補助金が29.1%、沿線自治体(フィレンツェ市とスカンディッチ市)の負担額は31.6%(各28.7%、2.9%)と3割強に過ぎない。
トラムの年間利用客数は年々、増えている。最初のT1路線が開業した2010年には775万人だったが、運行が通年になった翌年の2011年には1,215万人、その後も増加傾向を続け、2017年には1,408万人に。T1路線の東側起終点がカレ-ジ病院まで延伸した2018年(延伸開業月は7月)には1,914万人、空港と中心部のウニタ広場を結ぶT2路線が開業した2019年(開業月は2月)には3,452万人まで増えた。翌年の2020年はコロナ禍による市民の外出の抑制で減ったが、2021年には再び増加に転じ、2024年には3,916万人とこれまでの最高を更新。サン・マルコ広場まで延伸した2025年は4,000万人の大台に乗ることが見込まれる。先に述べたように、T3、T4を含めた「全路線が開業した暁には8,500万人台になる見込みだ」(プリオーニ部長)。
他のヨーロッパ都市でも言えるが、フィレンツェでもこれまで通勤などにマイカーを使ってきた市民らがトラムを利用するようになった。言い換えれば、公共交通を初めて利用する者を掘り起こしたわけである。こうしたことで、トラムの走っている地域ではマイカーの利用が減り、道路が慢性的にクルマで混んでいた渋滞問題も緩和されてきている。計画している4路線が完成した時には1日当たり6万5,400台のマイカーが減ると市は試算している。