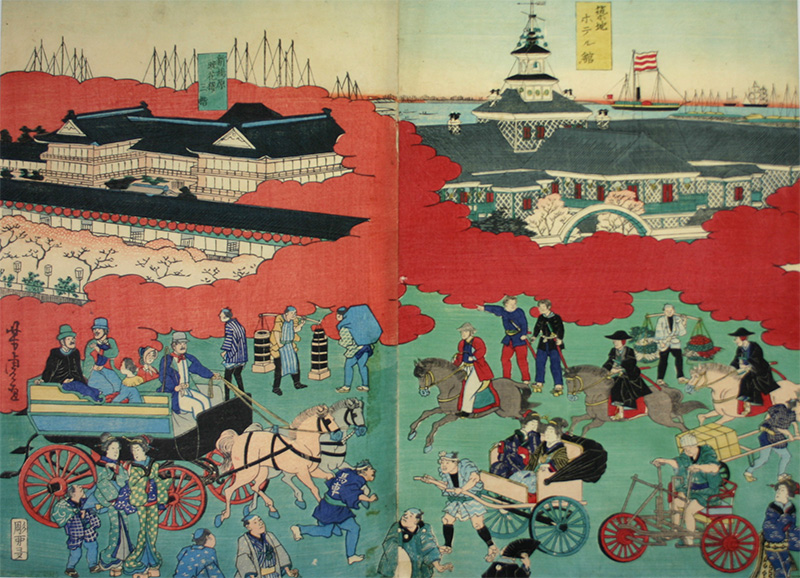2025.05.08
公共交通インフラはもう必要ないのか ――遅れている「持続可能な移動」、イタリアに学ぶ「国が前に出ること」
The Public-transport Infrastructure for Sustainable Mobility ――A Turning Point, When the Nation Should Step Forward: Learning from Italy as “Slow indicator”
7 / 7ページ
■「遅行指標」のイタリア、日本の奮起を促す羅針盤として期待
1990年代、ドイツやフランスなどでのトラムの復活や路線拡大の動きを「トラム・ルネサンス」と専門家は呼んでいたが、トラムの新規導入ではこれまでヨーロッパ主要国の中では後塵を拝していたイタリアでも着実に「トラム・ルネサンス」の軌道に入ってきたと言えるだろう。私はこのところ、こうしたイタリアの動きを世界的なトラム・ルネサンスのいわば「遅行指標」として重視し、その動向をウオッチし続けているが、それは「イタリアでも出来たのだから、日本でも世界におけるまちづくりの新しい流れをいつまでも傍観視してはいけない」との思いがあるからである。
日本では目下、国土交通省が音頭を取る形で、タクシーを含め移動手段のない「交通空白」地域の解消に向けて、一般ドライバーが自家用車を使って有料で客を運ぶ「ライドシェア」の導入が交通政策の大きな課題に位置付けられている。大都市や地方都市、過疎地域を問わず、「交通空白」の解消は大事である。そのために「ライドシェア」の導入拡大が図られることも解決策の一つとして必要だろう。ただ、気になるのは「交通空白」の解消イコール当面の交通政策のすべてのような雰囲気が国や自治体などの政策現場にありはしないかということである。
独立採算で何とか切り抜けてきた都市部における公共交通をめぐる経営環境も一段と厳しさを増している。従来からの需要減に運転手らの人手不足による供給減が加わり、都市部でのトラムや路線バスでも運行本数を減らす動きが広がっている。この結果、利用客数がさらに減少することで輸送力の一層の低下がもたらされ、利用客のさらなる減少につながる「負のスパイラル」の傾向が強まりかねないが、このことは単に交通の問題にとどまらず、移動環境が重要なカギを握る都市そのものの衰退につながるだろう。現在はまさに「交通崩壊」一歩前の状況であり、そうした認識がなければ、中長期的には一国の交通政策を誤った方向に舵取りすることになりはしないだろうか。
「交通崩壊」の危機という現状認識に立ったうえで求められるのは、日本の地域公共交通全体の構造的な問題解決、言い換えれば、地域公共交通を独立採算事業から公共(もしくは公的)サービスと捉え直し、イタリアを含め欧州のように運行頻度を上げるなどサービス水準を高めるために国の関与を強める独自財源制度など根本的な制度改革を急ぐことではないだろうか。
日本でも宇都宮市がトラムを新規に整備して注目されているが、それに続く動きがなかなか出てこないため、自治体の奮起を促す意見が専門家の間にも少なくないが、「持続可能な移動環境のための公共交通インフラ」は自治体主導で整備しようとしても限界がある。そろそろ、欧州のように国主導の思い切った制度改革をしていかないと、日本の都市そのものの衰退をも加速させてしまうだろう。